Notice: Undefined offset: 4 in /home/yakyuburo/yakyuburo.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 21
Notice: Undefined offset: 4 in /home/yakyuburo/yakyuburo.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 33
どうもみなさんこんにちは!カズズです。
今回は投手の先発能力をはかる上で重要なクオリティスタートについて記事にしていきたいと思います。
野球においてピッチャーの能力を評価する上で9イニングの間にどれくらいの点数を取られるかという防御率というのは重要な要素ですよね。
しかし、ピッチャーの能力というのは一口に防御率だけで語れるものではありません。
どれくらいのヒットを打たれたのかという被安打率や、どれくらい三振を奪ったのかという奪三振率などなど、実に様々な要素がありますよね。
そんなピッチャーの能力をはかるための様々な評価項目ですが、その中にクオリティスタートというものがあることをあなたはご存知でしょうか?
今回はそんな「クオリティスタート」という項目について解説・紹介していきたいと思います。
クオリティスタートの意味とは?
面白いことに、
【先発投手の #クオリティスタート(QS)の確率】がそのままセリーグの順位になっています!広島は、全試合の8割でQSを達成しているのだから、そりゃ強い。一方、阪神は…🥲#阪神タイガース pic.twitter.com/us7HG75slu
— チキンバレー from TigersCast (@ChickenValleyTC) April 19, 2022
クオリティスタート(以下QS)というのは、ピッチャーの能力をはかるための評価項目の一つで、日本語に訳すと良好な先発という意味になります。
そんなQSとは、いったいどんな能力を表す項目なのか?と言うと、先発投手が6イニング以上を投げ、自責点を3点以内に抑えたかどうか?という、先発ピッチャーの能力をはかるためのものです。
 カズズ
カズズ
Wikipediaなどでもこのように表現されています。ほぼ同じ意味あいですが参考までに。
クオリティ・スタート(Quality Start、QS、「良好な先発」)とは、野球における投手の成績評価項目の1つ。先発投手が6イニング以上を投げ、かつ3自責点以内に抑えた時に記録される。以下、本項ではQSと表す。
出典元:wikipedia
特にこのQSはメジャーからしてみれば非常に重宝される指標です。
先発投手は最少失点で、完封、完投できればいうことがありません。
しかしメジャーは日本のプロ野球と違い強打者がいっぱいます。
監督やコーチなどの首脳陣は先発ローテーションを守るピッチャーを確保するのに非常に気を使い球数などを調整します。
メジャーでは安定感が評価されます。ケガなく先発のローテーションを守ることだけでも至難の業です。
そんな中でやはり6回3自責点は十分先発投手の役割を果たしたといえる数字になっています。
先発ピッチャーが短いイニングで大量失点により降板されると、リリーフのピッチャーに負担がかかり疲労などでいつものパフォーマンスが発揮できず結果的にチームの勝敗にも関わってきます。
そういったことを防ぐためにもQSの指標を設けることによって、どのくらい先発投手の役割を果たすピッチャーなのか?
というのを明確にしてリリーフの負担を減らし結果的にチームの勝利に直結するかという意味でもQSは必要になってきます。
計測する上での注意点

このQSを計測する上で注意するべき点があります。
それは7イニング以降の自責点も参照しなくてはいけないと言う点です。
例えばある先発ピッチャーが6回までを投げ、自責点を2点に抑えて試合終了したという場合なら、QSとしてカウントすることができます。
しかしある先発ピッチャーが6回までを投げて自責点を2点に抑えたが、その後の7回で自責点3点を取られ、自責点は合計5点となったという場合はQSとしてカウントすることはできません。
 カズズ
カズズ
クオリティスタート率(QS率)とは?計算方法を解説!

QSを計算する方法は至って簡単です。
その公式はQS数÷先発としての登板数=QS率というもの。
 カズズ
カズズハイクオリティスタートとは?
HQS(ハイクオリティスタート):先発投手が7回以上を投げて、さらに自責点2点以内に抑えること
(QSは6回以上で3点以内)5/17だと40試合くらい消化してて、先発は週1回の登板なので…登板は多くても5回くらい?その全部HQSって相当すごいですが、廉なので!主人公様なので!w pic.twitter.com/6nsRp3lVAz
— 栗花落@アベミハ通販中 (@tsuyuri0315) May 19, 2021
余談ですが、QSにはさらに上の評価項目としてハイクオリティスタート(HQS)というものもあります。
このHQSの条件と言うのは先発ピッチャーが7イニング以上を投げ、自責点を2点以下に抑えるというものです。
QSよりもさらに厳しい条件となりますが、このHQSの率が高いピッチャーはチームにとっても大変ありがたい存在と言えますね。
 カズズ
カズズ
まとめ
みなさんいかがだったでしょうか?今回はクオリティスタート(QS)について書かせていただきました。
ここまでQSについて解説・紹介をさせていただきましたが、最後に一言!QSというのはあくまで投手の能力を測るための一判断材料でしかありません。
失点率や防御率というのは投球内容以外の部分でも変動する数値であるため、QS率が低いから悪いピッチャーと判断するのは早計です。
あくまでピッチャーの能力を測るための一要素であることを意識して、分析の材料にしてもらえればと思います。
こうしたデータを参照にすればするほど、野球の予想などがはかどって、おもしろ味が増していきますよね。
今後はQS率にも注目して、野球をもっと楽しんでいきましょう!
ではまた~。
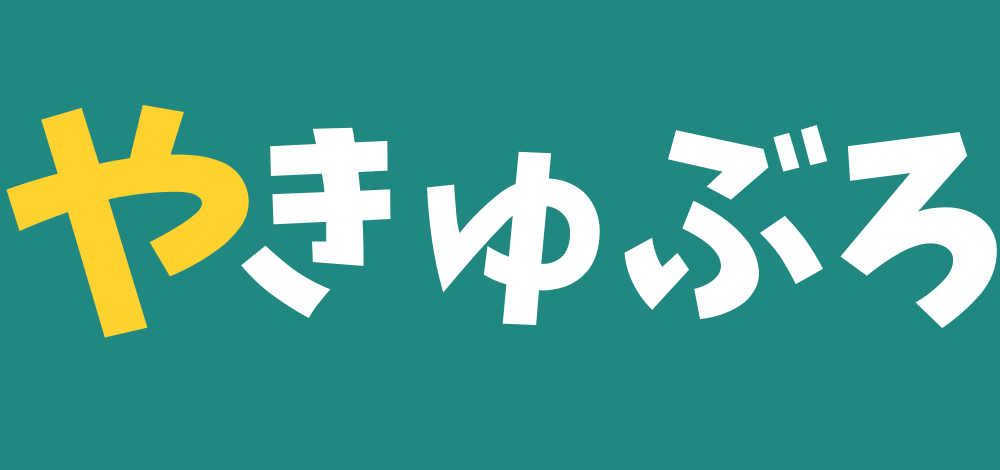

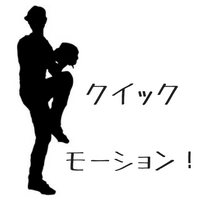

コメントを残す